 |
 |
| 私の場合は遠方のお客様ばかりを担当しているので、外出や営業に出た事はほとんどありません。担当顧客は関西圏が30%、関東圏が30%、その他が40%という感じです。チラシ等の広告物を通信販売している感覚です。遠くは北海道や、沖縄のお客様達と日々電話、メール、宅急便でやり取りしています。個人的感覚ですが、仕事の割合は、電話が40%、下請業者への指示、依頼が20%、デザイナーとの打合せが20%、残り20%が見積と事務等って感じです。仕事上、車の免許は必要ありませんが、もし免許があればもっと仕事の幅がひろがるなと思える部分はあります。仕事は通販的ではあるのですが、やっぱり「顔を見て商売」って部分も大事ですね! |
|
 |
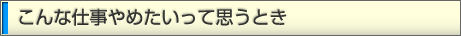 |
 |
| ほとんどのお客様が事前に予約、予定を知らせてくれるのですが、突然の企画や他社対抗上、急な仕事の依頼が時々あります。何とかその段取りをして、下請業者さんにも協力してもらい、ほとんどの依頼が納期も間に合わせて事なきを得ているのですが、努力も空しくその急な仕事がドタキャンされた時ですね。今までの努力はなんだったの?協力してくれた下請さんになんて言ったらいいの?キャンセルは仕方ないですけど、当たり前みたいに思ってる人とやり取りしている瞬間が一番辞めたい瞬間ですね。 |
|
 |
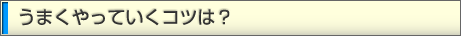 |
 |
| とにかくメモ、メモ、メモですね。仕事内容は本当に簡単です。見積と言っても料金表があるのですぐできますし、あとは広告が好きかどうか、おもしろいかどうか、だと思います。でも簡単な反面、件数が多く、電話や時期、納期が重なることも多くあります。1文字で全体がだめになるのが印刷物の特徴なので、どんな小さなことでも必ずメモる。聖徳太子には誰もなれませんもんね。メモのおかげで大きなミスは防げてます。 |
|
 |
 |
| はじめの1ヶ月は覚えたいこと、教えて欲しいこと、経験したいこと等も多くて結構遅くまで残ったりしていましたが、最近は仕事のコツもつかめて早く退社してますね。でも、たまにはお客さんからの「返事待ち」「修正指示待ち」「最終OK待ち」で泣きそうになることも・・・。遅くなるお客さんは決まってくるので、頑張ってコントロール(えらそうですみません)していくのが目標です。毎日ジムに通うぞ! |
|
